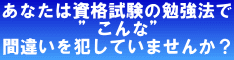1.不合格になるとき
試験のでき次第である程度合格、不合格は推測できます。不合格になったときに落ち込むのは自然なことですが、立ち直る方法はあります。まずは一晩寝てリセットし、気の合う友人や家族に話を聞いてもいいでしょう。もう一度勉強することは知識を定着させる良いチャンスですがなかなかその階段の一歩をあがれません。他人と比較する必要は有りませんが過去の合格者がどの程度の量をやっているかは調べておく必要があります。合格者の中には誇らしげにその量と質を誇張している人もいますがどの程度やったか詳細に説明してはいません。合格者の通りやる必要はありませんしやってはいけません。なぜならその合格者の人と自分の位置が違うからです。不合格になるときは試験のレベルにもよりますがほとんどが計画の無さと準備不足です。
2.なぜその試験に合格できなかったのか .
反省することはすぐ浮かんできます。最大な点は準備不足です。残酷な試験終了の合図がでて解答の回収が終わったらだいたい合格しそうなのか、しないのかがだいたい判別出来ると思います。専門学校のテキスト、問題集、あるいは市販のテキストや問題集のどれか一冊を繰り返しやったでしょうか。そしてその後、過去問を最低でも繰り返し最低5年分(5回分)そして95%以上正解するまで(出来れば100%)そして制限時間が半分以下になるまでやったでしょうか。どんな資格試験や入試でもその試験の形式、問題数、制限時間は制度が変更になっていない限り過去何十年も同じはずです。そして合格の最低ラインははどんな試験でもおおよそ70%以上のはずです。そうなら過去問を入手して最低5回分を繰り返し解くことです。これをやらないで試験の合格は難しいです。
こんな方法もあります
3.やり方がわからなかった
受験生の多くがやり方がわからなかった。勉強の方法を知らなかったという場合があります。試験の科目や内容の項目が多いなど、いろいろな場合があると思います。まじめな人は分厚い内容を頭から覚えようとします。このためにいつまでたっても最初の内容から先に進むことが出来ません。まるで底なしの沼に入ってそこから抜け出さないようになっています。そして気がついたらほとんど前に進んでいないのに目の前に試験の日が来ているのです。
4.科目別に全体を見渡すことが大事
試験の科目数とその科目の分野がどれだけあるのか。試験までの日数がいくらあるのか。何回ぐらいできるか。大まかに工程表を作ってみましょう。科目別に下記のような表を作ります。例えば「中学3年間の数学が1冊でわかる本」の項目とやったところは○をつけていくようなやり方です。最初の1回目はわからないところはどんどん飛ばして×をつけていきます。そして2回目、3回目と繰り返します。十分理解できていると思えるところは◎で、もうやりません。こうしてわからないところ、理解不足の×のところを重点にやっていきます。こうして試験までに一回もみたこともないというところがないというようにします。このような表を作れば自分がどこまで進んでいるのかどこが不得手なのかが一目でわかります。だいたいの事が把握出来たら過去問に取り組みます。この表は進行度合いに応じてそして本試験までの日数を考えて作り直す必要もあります。
| 項 目 | 1回目 | 2回目 | ・・・・ | ・・・ | N回目 |
| 1.正の数と負の数 | ○ | ◎ | |||
| 2.文式式 | ○ | ||||
| ・・・・・ | ・・ | ||||
| 8.因数分解 | × | ||||
| ・・・・ | ・・ |
◎:よくわかっているので次からしない ○:わかっている ×:今回は無視
ここである程度の知識の有る人、つまり学校で一通り習った、やったことがあってそれほど量がも多くない場合や過去問を見て項目だけ○×の正誤判定をさせるような内容でだいたい自信の有る解答が出来る人は、すぐ下の表にあるような過去問をやっていくことに移ってわからないところがあれば基本のテキストやネットで調べていくことです。
5.過去問も同じです
試験の科目がA,B,Cの3科目有ったとします。下記のようなの表を作って実際に時間を計って記録していきます。したがって5年間の過去問をやってみる場合は5枚の表が必要です。最初は制限時間の倍以上かかる科目があります。しかし何回もやっていくと同じものを繰りかえしていく作業だけをしていっているので、かかる時間は半分以下になります。
令和○○年度過去問
| 科目 \ 回数 | 1回目
時間 点数(自己採点) |
2回目 | ・・・・ | N回目 |
| A(制限時間:60分)
満点100 |
100分
40点 |
50分
60点 |
・・・・ | |
| B(制限時間:90分)
満点100 |
120分
30点 |
90分
50点 |
・・・・ | |
| C(制限時間:120分)
満点100 |
150分
20点 |
120分
60点 |
・・・ |
時間を計るのは100円ショップで買ってきたキッチンタイマ-です。カウンターとしても使えます。99分までしかセット出来ませんがほとんどこれで十分です。


6.予想問題も同じように
多くの資格試験や高校、大学入試では模試などが資格別、高校、大学別に市販されていますから上記の要領で同じような表を作って実際にやってみます。科目別に学習して過去問が制限時間の半分以下になって得点が自己採点で90%以上になっているなら模試でも制限時間内で70%は軽く超えているはずです。志望別の模試の回数は3回程度にします。本番では絶対に油断しないように。本番の独特な雰囲気と緊張は普段のものとは違います。
こんな方法もあります